溶接ヒューム規制③
~マスクの選定とフィットテスト編~
前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...
コラム
2022年~24年にかけて順次施行されている改正労働安全衛生法。
こちらの、改正内容について寄せられた質問などを取りまとめてご紹介します。
お問い合わせいただいた内容や、セミナーでの質疑応答などから、多くの事業者様に参考にしていただける内容を抜粋しています。
目次
A.リスクアセスメントの記録に特定の様式はありません。
従来、リスクアセスメント実施方法も厚生労働省から様々な資料が配布されていますが、固定された特定の手法はなく、記録の様式についても同様です。
自社に決まった手法や様式がなければ、リスクアセスメント実施支援ツール「CREATE-SIMPLE」を使用し、様式も参考にするのがお勧めです。
「CREATE-SIMPLE」の様式も義務ではないので、自社で必要な項目をアレンジしてもOKです。
▼リスクアセスメント手法の資料については下記をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/index.html
A.実務上は、既存の化学物質も実施が必要と考えます。
厚生労働省のQ&Aでは、実施義務があるのは対象物質を新規に採用したり、使用方法を変更したりといった場合です。
しかし、既存の対象物質についても「指針による努力義務」としており、既存のものでも安全面の対策が必要なことは変わりないため、事業場で使用する対象物質全てに対して、リスクアセスメントの実施と記録が推奨されます。
A.原則、すべての職場で行ってください。
リスクレベルは単純な上下で考えられるものばかりではなく、様々な条件の組み合わせです。
各職場の条件でアセスメントを行う必要があります。
A.現状のリスクアセスメント対象物質が含まれていれば、対象です。
ただし、「一般消費者用の製品」は対象から除外されます。
A.ラベルに必要な項目は以下です。
ただし、2,3,4,6については、SDSなどに危険有害性が分類されていない場合、記載不要です。
1,5,7の項目は有害性に関係なく必要です。
A.法律上、容器表示が難しい場合はSDSを備え付けることでも可能となっています。
ですので、SDSを参照とすること自体はNGではありません。
ただし、ラベル表示の目的を考えると「すぐに見られる」状態が必要です。
システム上のアクセスがスムーズに行なうことができ、トラブル時でもすぐに参照できる状態であればデジタル保管でも問題ないと考えます。
A.特定の様式はありません。
下記の内容が検討されたことがわかる内容であれば、様式は自由です。
A.建設現場は原則、衛生委員会の設置は不要です。
衛生委員会の設置は「常時使用する労働者が50人以上(業種により100人以上)」の事業場です。
建設現場は基本的に臨時のものですから「常時」の条件に当てはまりません。
作業員が所属する営業所などの事業場が50名以上だった場合に、各現場での安全管理を衛生委員会で検討することになります。
A.法で決められているのは下記の項目です。
少なくとも上記の項目を記録しておきましょう 3については、以下のようなイメージです。
「実験作業中に〇〇の瓶を倒し破損、一時的に吸引してしまった。気分不良を訴えたため、医師へ受診し、1日安静状態で経過観察となった。」
特定の様式は有りませんが、これらの項目を表にして、整備しておくと良いですね。
A.不要です。
対象業種はあくまで、その業種の業務(食料品製造業なら、食料品の製造)を行う場合が該当します。
食料品の製造を行わない場合は、会社としての業種が該当していても事業場は非該当となります。
A.対象ではありません。
日本標準産業分類では、「飼料・有機質肥料製造業」は中分類「飲料・たばこ・飼料製造業」に該当し、「食料品製造業」ではないため、対象ではありません。
A.濃度基準値設定物質などのばく露濃度を測定する際には、現状では資格要件はなく、バッジ型のサンプラーなどを使って測定すれば問題ありません。
作業環境測定は、個人サンプリング法が認められ、こちらは作業環境測定士による実施が必要なため混同しがちです。
どちらも知識と経験が必要なものですので、ばく露濃度の測定についても可能な限り有資格者に行わせることが推奨されています。
A.必ずしも外部の者でなければならないわけではありません。組織内部の者でも資格要件を満たせば結構です。
ただし、労働災害の再発防止という観点から、外部の者であることが望ましいとされています。
A.事業場に1名で構いません。
事業場に複数名選任することも可能ですが、作業職場ごとに選任する必要はありません。
A.法律上は、専属の規定がないので複数事業場の兼任を明確に禁止してはいません。
ただし、事業場での化学物質管理を行うためにはその事業場に所属する者であることが望ましく、行政も各事業場で1名にするように指導することが予想されます。
A.直近の作業環境測定の結果のみでは、判断ができません。
下記の3条件をすべて満たす場合に、通常6か月の頻度を1年に緩和することができます。
※四アルキル鉛は作業環境測定が義務付けられていないため、②③を満たせばOK
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム
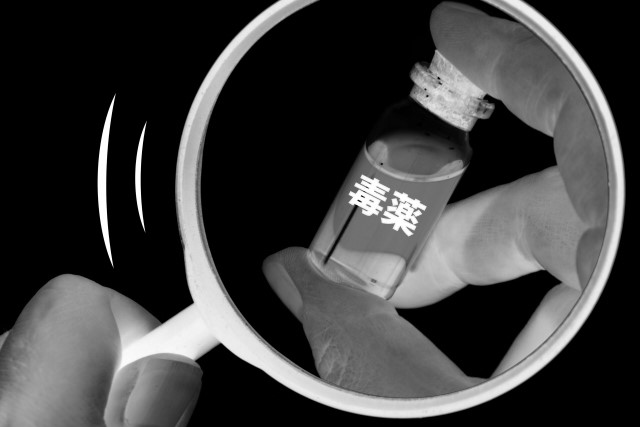
前回のコラムでは測定によって0.05mg/m3以上となった場合は、対策を講じなけ...
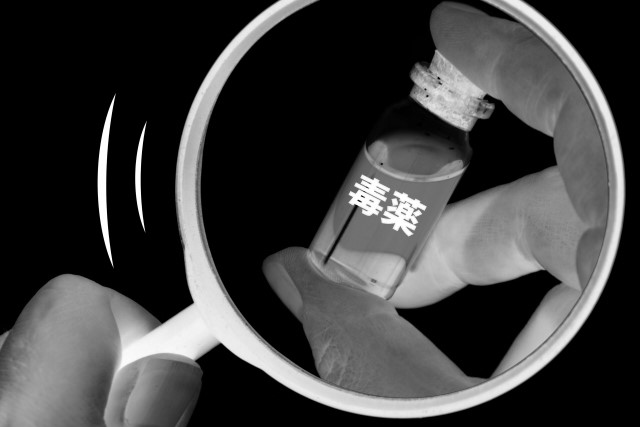
前回は、溶接作業が屋内継続作業に当たるかどうかの基準を確認しました。 今回は、屋...
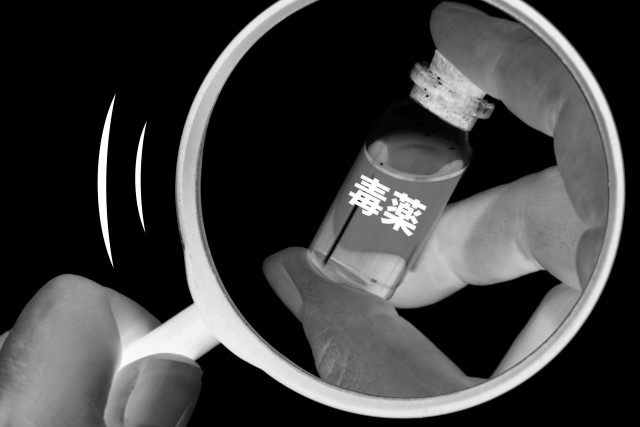
溶接ヒュームは、令和3年4月1日以降、段階的に規制強化の改正が施行されています。...

職場で化学物質を使用する場合「有害性の掲示」が必要な物質があります。この「有害性...