『安全配慮義務』とは
安全配慮義務という言葉は皆さんご存じかと思います。しかし「安全配慮義務について具...
コラム
コラム『安全配慮義務とは』でご紹介した一般的な基準は、法律で定められた最低基準です。しかし、実際には個別の事情に応じた事業者の安全配慮が必要です。この点が、安全配慮義務の曖昧さの原因となっています。今回は事例を用いて、深掘りしていきます。
もし事故が発生した場合には、事業者が安全配慮義務を果たしていたか否かを最終的に裁判で判断することになります。
ここで1つ事例を紹介します。古い判例ですが、宿直勤務中の職員が盗賊に襲われたという事件です。非常にイレギュラーなケースではありますが、この事例では、安全配慮義務を怠ったとして事業者に損害賠償を命じる判決が下されました。この判断の背景には、宿直勤務中の防犯対策や、万が一盗賊が侵入した場合でも被害が及ばないよう施設を工夫する必要があったという点が挙げられています。
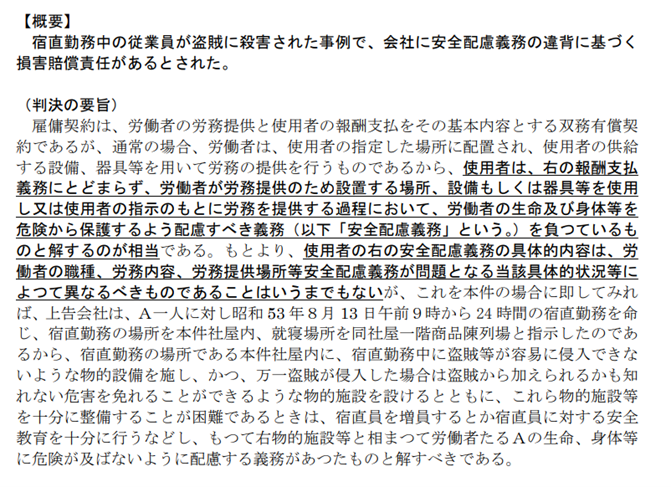
川義事件(最高裁昭和 59 年4月 10 日第三小法廷判決)
厚生労働省資料:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf?utm
上記の事例では、「いや、さすがに盗賊が押し入ってくることまでは想定できないよ」という声が聞こえてきそうですが、このように安全配慮義務には「ここまでやれば十分」という明確な基準がないことがご理解いただけるかと思います。現場ごとの状況を踏まえ、その現場に応じた危険をさまざまな角度から想定し、対策を講じることが求められます。そして、その対策をPDCAサイクルで継続的に見直していくことが必要です。この考え方は、多くの職場で行われているKY(危険予知)活動にも通じるものです。
さらに近年の改正では、事業者の安全配慮義務範囲が「労働者」から「作業に従事する者」に拡大されています。
この改正は特化則、有機則などが規制する「有害な作業」については2024年4月、クレーン則、ボイラー則などが規制する「危険な作業」については2025年5月に施行されます。
自ら雇用する事業者だけではなく、下請業者や出入りの業者にも「安全配慮義務」が適用されるのです。
従来の対象範囲である「特化則」や「有機則」は、事業場の中でも取り扱うエリアが限定されていることが多く、立ち入る作業者も限られているため、影響範囲も比較的少ないケースが多かったのですが、今回の改正で物理的な危険も広くカバーされ、一気に対象範囲が広がりました。そこで、具体的な対象をまとめると以下のようになります。
・危険な場所への立入禁止、特定の場所での喫煙禁止、事故発生時の対処等の対象範囲を「労働者」から「作業に従事する者」に拡大
・「作業に従事する者」は、現場監督や資材の搬入、荷卸しなど、直接作業に関係しない者も含まれる
「クレーン」など、事業場で比較的多くの作業者が出入りするエリアにおいて使用される設備が指定され、「資材の搬入、荷卸しなど、直接作業に従事しない者」も対象に含まれるとされています。そのため、結果として安全配慮の対象範囲がかなり広がったことが分かります。
自社の事業場に出入りする作業者は、全面的な対応が必要になるかもしれません。
セミナーインストラクターとして、数々のセミナーを担当。オンラインセミナーの実施やeラーニングシステムを使った動画コンテンツの制作にも注力する。コンテンツの企画から講師までを一貫して手掛け、通年80回以上の講師実績を持つ。また、イーバリューの法令判断担当として、クライアントの法解釈に関する質問や相談に対応。対応件数は年間約1,000件に上る。法令知識だけでなく、省庁や管轄自治体等の行政への聞き取り調査も日常的に行っており、効果的な行政対応のノウハウを持つ。

その他のコラム

安全配慮義務という言葉は皆さんご存じかと思います。しかし「安全配慮義務について具...

現場でよくある事故事例、今回はフォークリフトにまつわる事例をご紹介します。 目次...
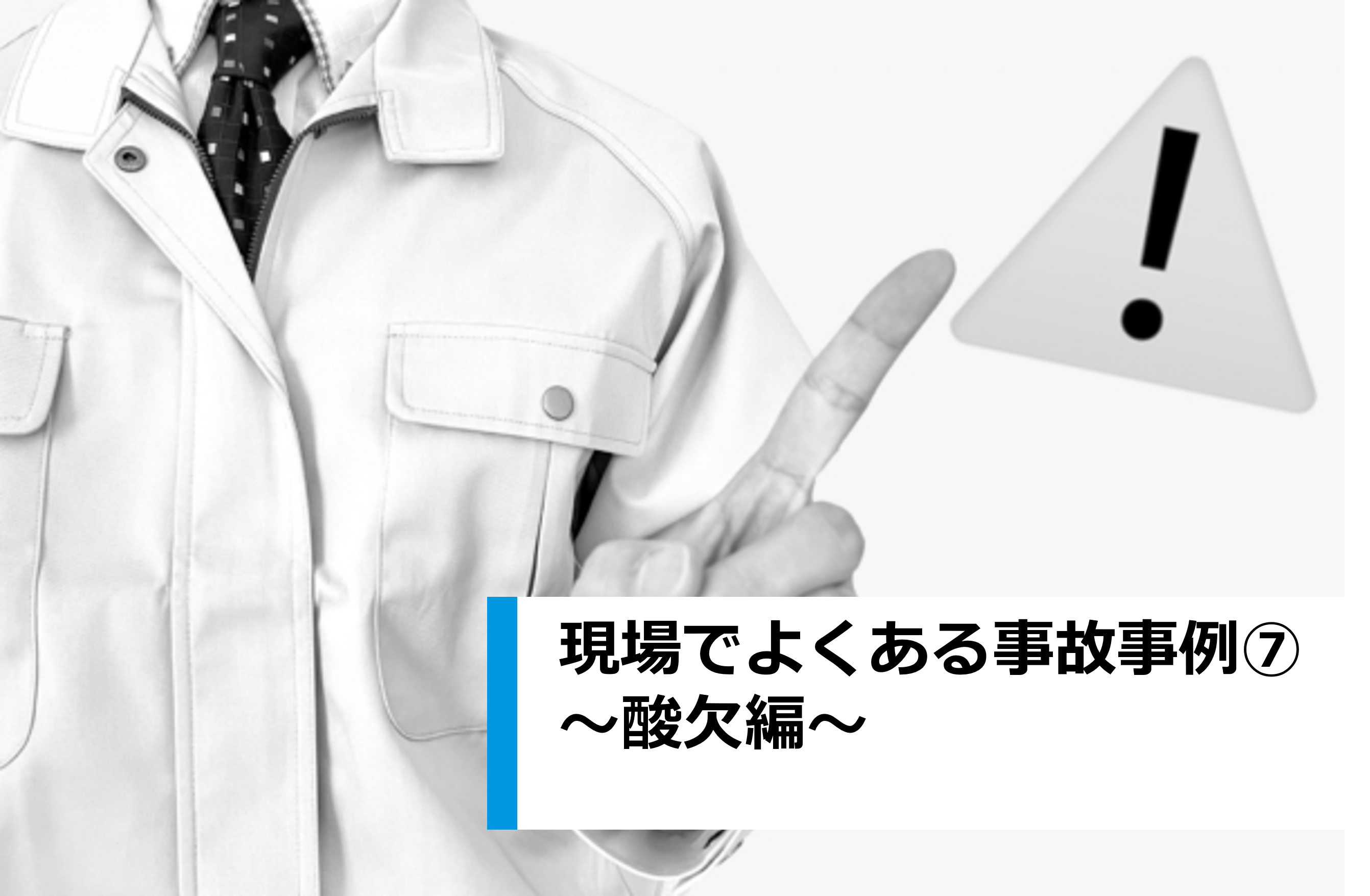
現場でよくある事故事例、今回は酸欠にまつわる事例をご紹介します。 目次1 消石灰...
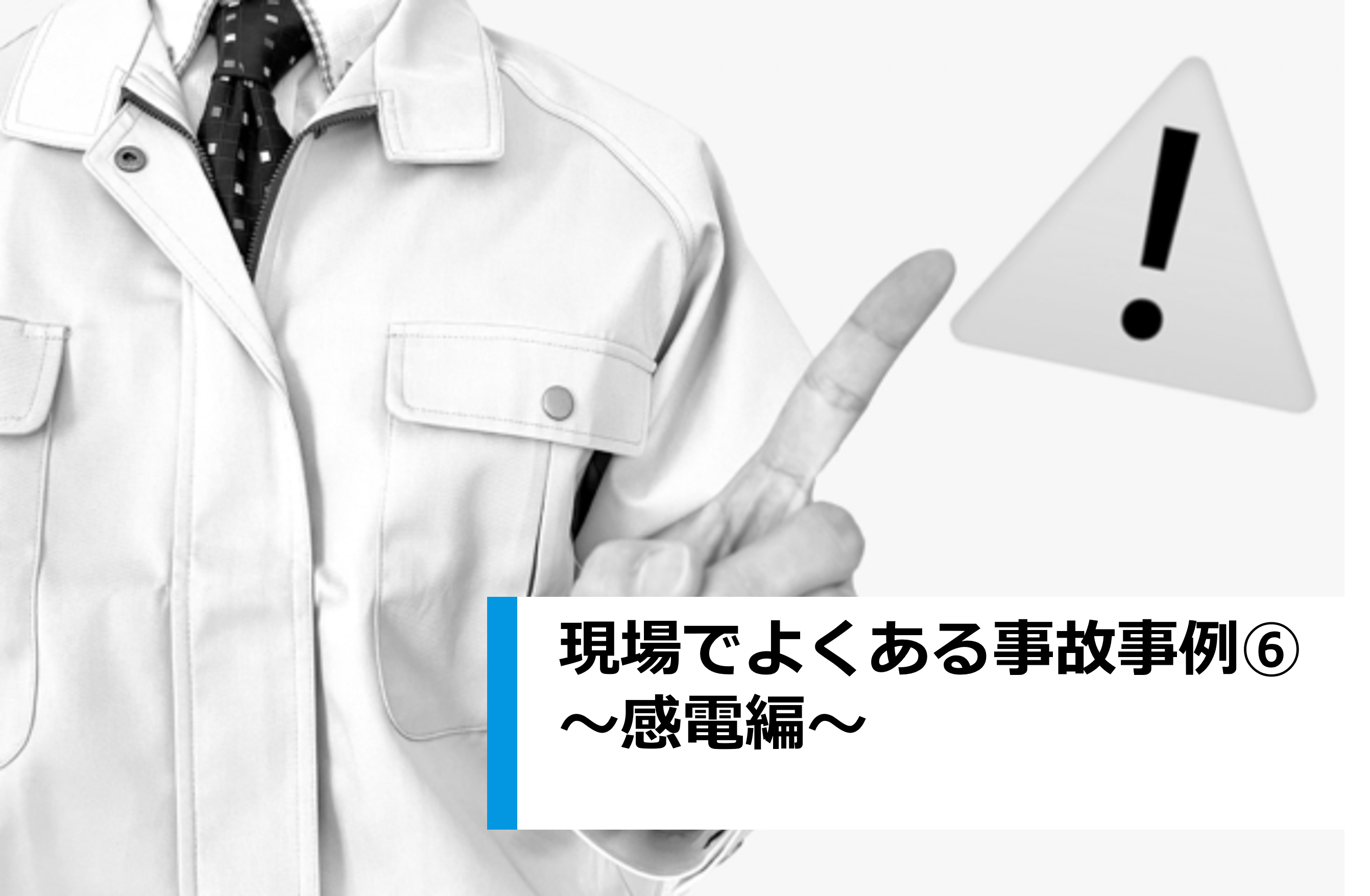
現場でよくある事故事例、今回は感電にまつわる事例をご紹介します。 目次1 高所作...